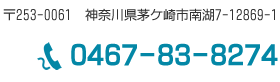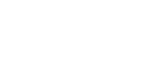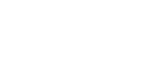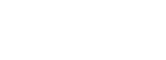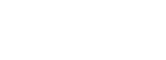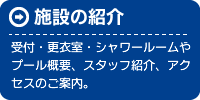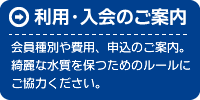2025/03/19
西浜小学校2年生の庭園観察
3/13(木)西浜小学校2年生100余名が小山先生らの引率で冬の庭園観察にやってきました。いつもやってくる2月から一月ほど経った庭園は春の気配も感じられるようになっています。梅が終わり桜の花芽が膨らんでいる、椿が咲き樹下に落花するまでになっている、ホトケノザなどが春告げんとそこここに咲き始めた。子供たちはそれぞれの情景をスケッチしていました。ひょうたん池の向こうでは、ウッドチップの小山でテントウムシの幼虫探しが賑やか、更にその向こうではウッドチップづくり見学のグループが植栽担当の話を聴いていました。1時間余りの観察は瞬く間に過ぎて春夏秋冬4回の庭園観察が締めくくられました。新緑の頃には、新しい2年生が来てくれるかな。


(以下、柴橋さん投稿です 2025/03/20)

プール棟正面の門から入って右側に咲く梅は、江南所無(コウナンショム)という品種ではなかろうかと、昨年の今頃に推定しました。昨年までは不思議なことに香りを感じることがなく、それが同定への一つの不安材料だったのですが、今年は良い香りを楽しむことができました。花の香りは、開花してからの時間や、1日の中の時間帯、気温や湿度などの気象条件などに複雑に依るのかも知れません。

気温の変動が大きいものの、彼方此方で春の野の花が咲き始めました。一番手はホトケノザ(仏の座)。1月初め頃までは花弁が開かずに閉鎖花が殆どだったのですが、今はこの通り、特徴的な形の花が明るい春の光の中で生き生きと咲いています。2枚の葉が茎を抱く様に丸く広がって段重ねになっている上に花を咲く様子を、蓮華座と仏像に喩えてこの名で呼ばれるのでしょう。

開花しかけた状態の清楚な姿のオニタビラコ(鬼田平子)。変わった名前ですが、田に平らに張り付くように放射状に葉が伸びているので田平子と呼ばれる草があり、それより大きめなのでオニを頭に付けられたのだとか。先に挙げたホトケノザの名は春の七草の一つですが、それはタビラコのことを指しているのだとか。タビラコの放射状に伸びる葉の様子を見れば、それも納得ですが、紛らわしいこと甚だしいです。

ホトケノザより少し遅れてヒメオドリコソウ(姫踊子草)の登場です。密に詰まった葉の間から顔を覗かせている姿は、厚いコートを着込んでで着膨れしている様で、名前に反して、軽やかな動きを連想させるのは難しい様な…

これも春の野の花の代表選手、オオイヌノフグリ。この小さな青い花も多くは夕方には落花してしまうのですが、次々に新しく咲くので、全体で見るといつも沢山の花でいっぱいです。

こちらはフラサバソウ(フラサバ草)。オオイヌノフグリより一回り、もしくは二周り小さな可愛らしい花です。フラサバとは、フランシェとサバティエという二人のフランス人の名前を組み合わせたものだそうです。茎が地に這って広がるので、その一角はぎっしりと緑に覆われています。

これまた春の野の花の代表選手、コハコベ(小繁縷)。春の七草の一つハコベラ(繁縷)とはこれのことです。燕脂色の葯。その一つは既に花粉を出しています。真ん中に見える3本の花柱はオバQの頭の毛の様です。花弁は5枚なのですが、それぞれ深い切り込みが入っているので、一見すると10枚の様に思えてしまいます。

カラスノエンドウ(烏野豌豆)も広く知られる春の野の花です。蜜腺が花の外にあることでも知られています。蟻が寄ってきているのも、実は花ではなくその花外蜜腺に引き寄せられたものなのでしょう。

白い小さな可愛い花なのですが、花よりも、その真ん中からどんどん真っ直ぐ上に伸びていく姿の方に気を取られてしまいそうなのは、ミチタネツケバナ(路種漬花)。伸びているのは種の入った鞘。そんな姿からも分かると思いますが、アブラナの仲間です。

草叢の中からスッと伸び出た小洒落たランプスタンドの笠といった風情の編笠たち。その名もアミガサユリ(編笠百合)です。鱗茎部分が貝が合わさった様に見えることから、バイモ(貝母)という名前もあるそうです。葉の先端はやがて巻き髭状になり、何にでも巻き付いて細い身を支えるようになります。
Copyright (C) 2019 太陽の郷プールガーデン. All Rights Reserved.