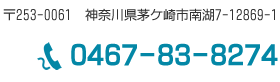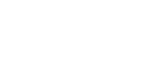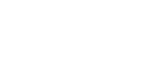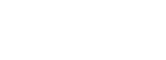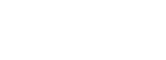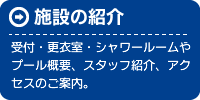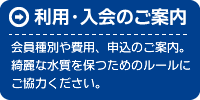2025/04/16
藤
プール駐車場脇の藤棚の花芽の膨らみが目にとまったのは3月も末の頃でした。それから2週間余り、花芽は日に日に大きくなって先ずは藤棚の向かって左側が薄紫の花房を垂れています。もうじき右側が、そして最後に中央部の白房へと開花は進んでいきます。昨秋、植栽が2年後、3年後を見据えて、強めの剪定を入れたのでした。それでもこれだけの花房を付けてくれました。そこここの樹々も少しずつ緑を色濃くして、庭園は春たけなわを迎えようとしています。一房手折りて上着の胸ポケットに挿し、さっそうと春の街へと出掛けてみませんか。


(4/17 以下、柴橋さん投稿です)

三週間前に紹介したスズメノヤリ(雀の槍)は、雌蕊が枯れ、代わりに雄蕊が伸び出て、雄性期となりました。

芝生の中にスズメノヤリと共に目立つのはカラスノエンドウですが、同じ様に巻きひげの蔓を伸ばすマメ科の小さな白い花は、スズメノエンドウ(雀野豌豆)。小さいという意味でスズメが冠せられている点は、スズメノヤリと共通しています。

同じくマメ科のカスマグサ。カラスノエンドウとスズメノエンドウの中間的な大きさなので、両者の名の最初の音を取ってこの名前。巻きひげの性質は三者共通ですが、花の方は、大きさもですが、それぞれの形からでも容易に区別できます。

もう何度も紹介していますが、満足度の高い写真が撮れたのでもう一度。お馴染みのコハコベ(小繁縷)です。いつもピンとした姿の花なので撮し易いのです。

この花を見ると、コハコベの花が大きいと感じてしまいます。直径約2ミリの淡青紫色の花を咲かせているのはキュウリグサ(胡瓜草)。葉を揉むと不思議なことにキュウリの匂いがすることからこの名前です。こんな小さな花ですが、花弁は銀を織り込んだラメの様な生地なのですね。芝生の中あっても、その小ささにも拘らず目に付くのも道理です。

花の小ささは、これも同じ。ヤエムグラ(八重葎)です。こんなに小さくても虫媒花。雄蕊に雌蕊、花弁もあります。ヤエムグラと聞くと、百人一首に収録されている、恵慶法師の詠んだ「八重葎 茂れる宿の寂しきに 人こそ見えね 秋は来にけり」を思い起こす方も多いのではと思います。ヤエムグラの花は春なのに、なぜ秋なのか不思議な気がしますが、そこでの「八重葎」はこのヤエムグラを指しているのではなく、一般的に葎(むぐら)と称される各種の雑草が八重にも重なるほどに茂っている状態を指していると解釈されている様です。ですがヤエムグラは目立つ花ではありませんし、寧ろ「ひっつき虫」としての方が馴染みがあると思うので、「八重葎」もこのヤエムグラなのかも知れないと思ってしまいます。

ひょうたん池の周りに沢山の黄色い可愛らしい花が咲いています。ヘビイチゴ(蛇苺)です。その姿には蛇を思い起こさせる様なものは何もないのですが、蛇が食べる苺という意味なのか、蛇が居そうな湿った場所に生育するという意味なのか… ヒトが食べても毒ではないものの、美味しいものではないそうです。

小径を挟んで池の向かい側の芝生に、紫色の花が地に這う様に群生しています。キランソウ(金瘡小草)です。「キ」は紫を意味する古語、「ラン」は同じく藍色を意味するそうで、花の色がこの名の由来だとする説明もあるようです。では、紫色なのに漢字名には「金」とはこれ如何に。漢字表記の「金瘡」とは刀傷のことで、この葉を潰して傷に塗ると治癒に効用があることを意味しているのだそうです。名前は兎も角として、レンズを向けたくなる花です。

レンズを向けたくなる紫色の花をもう一つ。庭の西北、桜の杜に咲くタツナミソウ(立浪草)です。キランソウと同じくシソ科なので花の形はどことなく似ていますが、キランソウが花も地を這うように咲かせているのに対し、タツナミソウは、その名前の通り、泡立って寄せくる波を思い起こさせる様に、何もなかった(様に見える)所からいきなり直立して咲き出します。

ひょうたん池の南西近くの一隅に青いハナニラ(花韮)が群生しています。普通に目にするハナニラの多くは白で、周辺部分が紫味を帯びたものもよく見ますが、ここまで青い花が群生しているとは。グーグルで検索してみると、ハナニラの中のジェシーという名の園芸種の様です。
<<「梅」前の記事へ
Copyright (C) 2019 太陽の郷プールガーデン. All Rights Reserved.