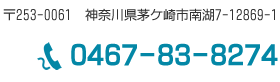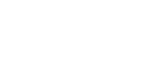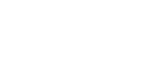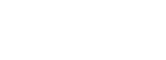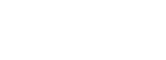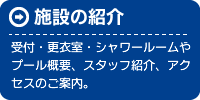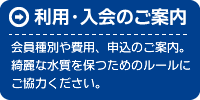2025/04/02
カラスノエンドウ
カラスノエンドウが庭園の至る所で育っています。場所によっては伸び放題、もうじき刈られる定めですが、食べられると言うので試してみました。最初はおひたし、次に卵とじ、そして天ぷら。いずれも先っぽの茎がまだ柔らかいのがいいようです。食感としては、あまり特徴が感じられませんでしたが、物珍しらしさを楽しませて頂きました。庭のカラスノエンドウには2、3日経つとアブラムシがびっしり、滲み出てくる蜜がご馳走なのですね。花が終わると、エンドウ豆が出来てきます。豆がまだ青いうちに摘んで塩茹でし、お握りにまぶしているレシピがありました。それぞれにいろいろな楽しみ方があるようですが、アブラムシのが一番でしょうか。


(4/3 以下、柴橋さん投稿です)

庭の北西部に咲く大木の桜は、桜の代表樹種であるヤマザクラ(山桜)でしょうか。褐色味を帯びた葉芽と淡紅色の花が同時に展開し、その花の何とも芳ばしい香りが堪りません。日本の桜には沢山の種類がありますが、本来の野生種は10種類ほどなのだそうです。ヤマザクラはその一つ。山に自生しているからこの名前なのでしょうから、数は多い筈、吉野の桜も多くはヤマザクラだそうです。

プール棟北側に咲く大木の桜は、オオシマザクラ(大島桜)でしょうか。葉と花が同時に展開するのはヤマザクラと同じですが、こちらは緑の葉で花は白色ですから、区別は容易です。葉の青っぽい香りも強いのですが、花自身はヤマザクラの香りとはまた違うこれも芳ばしい香りです。桜餅に使われる葉はオオシマザクラだそうです。名前のオオシマとは伊豆大島のことだそうです。

プール棟北側を通って庭に向かうところに低木の桜が咲いています。しかも昨年の10月から、極寒期の短い休みはあるものの、咲き始めてほぼ半年間も。シキザクラ(四季桜)です。春の今頃の方が秋の頃よりも花は大きい様に思います。花が咲き続けることの代償なのか、香りは全くと言っても良いほど感じられません。

そこから西へ進むと3月上旬にはいち早く早咲きの緋桜が咲いていました。カワヅザクラ(河津桜)か、その仲間でしょうか。それからひと月も経つので、これは最後の数輪になるのでしょう。この大木のほか、藤棚のやや西にも小柄な同種の若樹が花を沢山付けていました。実に芳しい香りでした。

旧第一病舎の東側に、華やかにソメイヨシノ(染井吉野)が咲いています。江戸時代末期から明治期に、現在の東京都豊島区駒込、当時は染井村の植木職人が、エドヒガンとオオシマザクラから交配して作り出し、奈良の吉野に行かずともその桜を楽しめるという触れ込みで吉野桜の名称で売り出したものを、のちに吉野のヤマザクラと区別するために「染井吉野」と名付けられたと言われています。歴史は浅いのですが、葉に先んじて樹木一杯に華やかに咲く姿もあって、いまや桜の代表格。色といい、香りといい、花つきといい、確かに代表に相応しいものです。成育の早さも特徴で、日本各地に桜の名所が次々と出来たのも、ソメイヨシノの成長の早さのお陰です。

庭の北部に2本、ジンダイアケボノ(神代曙)の若い木が育っています。各地で大規模にソメイヨシノだけを植栽したがために、その病虫害が蔓延し易くなり、その病虫害に強いとされるジンダイアケボノが後継として植えられる傾向にある様です。ソメイヨシノよりは花色が濃く、グラデーションの美しい花です。1991年のことだそうですからごく最近なのですが、調布にある東京都神代植物公園に原木があるのでこの名が付けられたのだそうです。香りはやや弱く、この点だけはソメイヨシノの代替としては少々物足りません。

旧第一病舎の西側脇に緋色で目を引く緋桜が咲き誇っています。蕾は緋色よりも更に色濃く、赤紫色くらいに見えますが、花開くと、花脈が透ける優美な花弁は桃色か牡丹色です。正門からも色合いが目立っています。香りは極めて弱く、殆どしないと言っても良いほどです。

その緋桜の北側隣にキブシ(木五倍子)が淡黄色の花穂を垂れ下げ、春の風に靡かせています。花芽としては咋秋から垂れていましたから、長い蕾期間を経ての開花です。難読な漢字名は、そもそもヌルデ(白膠木;これも難読漢字ですね)の木にできて、染色、薬用に有用なフシ(五倍子)と呼ばれる虫瘤の代用として、この木の果実が使われたから、ということに由来しているのだとか。山地や丘陵などよく見かけます。

旧第一病舎東壁傍には小さな白い壺型のアセビ(馬酔木)の花が穂を成して垂れています。鼻を近付けると良い香りです。馬が食べると毒にあたって酔った様な足取りになってしまうことから、この難読漢字名になったのだそうです。キブシ同様、花芽としては咋秋から垂れていましたから、長い蕾期間を経ての開花です。

芝生に目を遣ると、スズメノヤリ(雀の槍)がニョキニョキと。つい花の部分のみを接写してしまいがちなのですが、今回は全体を。茎の先端の花序を大名行列の際の毛槍に見立て、著しく小さいことを意味する雀を冠したのが名前の由来だとか。命名者たるには逞しい想像力が必要な様です。
<<「水仙」前の記事へ
Copyright (C) 2019 太陽の郷プールガーデン. All Rights Reserved.